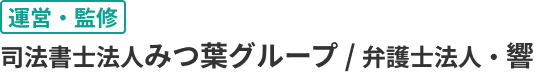借金を返済できない!正しい対処法と返済不能となった場合の末路についても解説


借金の返済期日までにお金を用意できない場合、まず行うべきは今置かれている状況を整理することです。
借金を返済できない時の対処法は、状況によって次のように異なります。
- 借金の滞納が2ヶ月以上続いている(続きそう)
→弁護士・司法書士に相談して債務整理を検討する - 一時的に返済資金を確保できない(できない可能性がある)
→借入先に返済日・返済額の調整を相談する - 返済中に無職になった・収入が減少した
→公的融資制度・給付金などを活用する
2ヶ月以上滞納している、もしくは長期的に返済ができなくなりそうといった場合は「債務整理」を検討しましょう。
弁護士や司法書士に「債務整理」を依頼することで、債権者(お金を貸した側)からの督促を止め、月々の返済負担を軽減できる可能性があります。
当事務所では、借金が返済できずお悩みの方のご相談を無料で受け付けております。
状況に合わせて解決方法をアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。
この記事では、借金を返済できなくなった場合の対処法や滞納のリスクについて、詳しく解説していきます。

目次 [表示]
借金を返済できないときの対処法は?
借金の返済ができない状況や理由によって、対処法は次のように異なります。
- 借金の滞納が2ヶ月以上続いている(続きそう)
→弁護士・司法書士に相談して債務整理を検討する - 一時的に返済資金を確保できない(できない可能性がある)
→借入先に返済日・返済額の調整を相談する - 返済中に無職になった・収入が減少した
→公的融資制度・給付金などを活用する
それぞれの対処法について、詳しく解説していきましょう。
司法書士に相談して債務整理を検討する
借金が返済できずに2ヶ月以上が経過している、または経過してしまいそうな場合は、「債務整理」が選択肢の一つに挙げられます。
債務整理とは、債権者(お金を貸した側)との交渉または裁判所への申立てによって、借金の減額・免除を目指す方法のことです。
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの方法があり、それぞれに効果やデメリットが異なります。
- 任意整理:毎月の返済額を下げたい人向け
債権者と直接交渉し、将来利息や遅延損害金のカットを目指す方法。交渉後は、借金残高のみを3〜5年かけて返済していくことになる。 - 個人再生:住宅を守りながら借金を減額したい人向け
裁判所に申し立て、借金残高を5分の1~10分の1に減額する方法。条件によっては持ち家を残すことができる。 - 自己破産:まったく返済できないときの最終手段
裁判所に申し立て、ほぼすべての借金の返済義務を全額免除してもらう方法。預貯金や給与、不動産、自動車などの財産が差し押さえられる可能性がある。
一般的に多く利用されるのは「任意整理」です。デメリットが少なく、将来発生する予定の利息をカットすることで、返済額を減らすことができます。
ただし、どの方法にもデメリットもあるので、まずは法律の専門家である弁護士や司法書士に相談してみましょう。
専門家に相談することで、自身の状況にあった対処法を提案してもらえます。

借入先に返済日・返済額の調整を相談する
一時的に資金を確保できず、借金を返済できない場合は、ローン会社やクレジットカード会社などの借入先に相談しましょう。
カードローンやキャッシングであれば、返済期日の延長や返済額の調整に対応してもらえるケースがあります。
クレジットカードの支払いの場合は、分割払いやリボ払いへの切り替えに切り替えられる可能性があります。
いずれも期日を過ぎてしまうと遅延損害金が発生してしまうため、返済できないとわかった段階で早急に連絡しましょう。

相談する際は「返済が難しい理由」に加え、「返済できそうな金額」「返済できそうな期日」といったことも明確にしておくとスムーズです。
公的融資制度・給付金などを活用する
返済中に職を失う、収入が減るといったことが原因で生活に困窮し、返済ができない場合は、次のような公的融資制度・給付金の利用を検討しましょう。
| 緊急小口資金 | 低所得世帯が緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に受けられる融資。 |
|---|---|
| 福祉資金 | 低所得世帯や障害者・高齢者がいる世帯に対する一時的な融資。 |
| 総合支援資金 | 失業や減収などで生計維持が難しい世帯に対し、生活の立て直しのために受けられる融資。 |
| 住居確保給付金 | 離職や廃業など、やむを得ない状況により住居を失った、または失う可能性がある場合に受けられる給付金。 |
それぞれの制度内容について、詳しく解説していきましょう。
緊急小口資金
緊急小口資金は、一時的に生計の維持が困難となった場合に受けられる融資制度です。
貸付条件は、次のように定められています。
| 貸付対象 | 以下の条件に該当する世帯が対象。 ・低所得世帯である ・緊急かつ一時的に生計維持が困難な状況である ・返済(償還)の見通しが立つ |
|---|---|
| 貸付限度額 | 10万円以内 |
| 据置期間(※1) | 貸付けの日から2ヶ月以内 |
| 償還期限(※2) | 据置期間経過後12ヶ月以内 |
| 貸付利子 | 無利子 |
| 連帯保証人 | 不要 |
参考:緊急小口資金のご案内 - 東京都社会福祉協議会
※1:元金の返済は発生せず、利息のみの支払いをすればよい期間のこと。この場合は無利子のため利息の支払いも不要。
※2:返済が完了するまでの期限のこと。
あくまで貸付けなので返済する必要がありますが、連帯保証人不要で無利子なので、融資のハードルが低く負担も少ないといえます。
福祉資金
福祉資金は、低所得世帯や障害者・高齢者がいる世帯の生計の安定を目的に設けられた融資制度です。
貸付条件は、次のように定められています。
| 貸付対象 | 以下の条件のいずれかに該当する世帯が対象。 ・必要な資金を他から借りることが困難な「低所得者世帯」 ・障害者手帳などの交付を受けた人が属する「障害者世帯」 ・65歳以上の高齢者が属する「高齢者世帯」 |
|---|---|
| 貸付限度額 | 資金の用途に応じて上限目安額は異なる。以下は一例。 ・生業(自営業)を営むために必要な経費:460万円 ・病気、負傷の治療経費、介護サービスなどの介護費用、療養期間中の生活費:170万円 ・結婚、出産、葬祭、転宅に際し必要な経費:50万円 ・就職時の支度に要する経費:50万円 ・低所得者、障害者、高齢者が日常生活上一時的に必要な経費:50万円 ・給排水設備、電気設備もしくは暖房設備を設けるのに必要な経費:50万円 |
| 据置期間(※3) | 貸付けの日から6~12ヶ月以内(資金の用途により異なる) |
| 償還期限(※4) | 据置期間経過後3〜20年以内(資金の用途により異なる) |
| 貸付利子 | 無利子(連帯保証人を立てない場合は年1.5%) |
| 連帯保証人 | 原則必要(立てない場合も貸付は可能) |
参考:厚生労働省公式サイト「生活福祉資金貸付制度」
※3:元金の返済は発生せず、利息のみの支払いをすればよい期間のこと。無利子で融資を受けた場合は利息の支払いも不要。
※4:返済が完了するまでの期限のこと。
あくまで貸付けなので返済する必要がありますが、連帯保証人を立てれば無利子となり、償還期限も長めに設定されています。
総合支援資金
総合支援資金は、失業や減収によって困窮した際、生活再建を目指すために受けられる融資制度です。
貸付条件は、次のように定められています。
| 貸付対象 | 失業や減収などにより生活が困窮している世帯。 |
|---|---|
| 貸付限度額 | 生活支援費:月20万円以内(単身世帯は月15万円以内) 住宅入居費:40万円以内 一時生活再建費:60万円以内 |
| 据置期間(※5) | 貸付けの日から6ヶ月以内 |
| 償還期限(※6) | 据置期間経過後10年以内 |
| 貸付利子 | 無利子(連帯保証人を立てない場合は年1.5%) |
| 連帯保証人 | 原則必要(立てない場合も貸付は可能) |
参考:厚生労働省公式サイト「生活福祉資金貸付条件等一覧」
※5:元金の返済は発生せず、利息のみの支払いをすればよい期間のこと。無利子で融資を受けた場合は利息の支払いも不要。
※6:返済が完了するまでの期限のこと。
あくまで貸付けなので返済する必要がありますが、連帯保証人を立てれば無利子となり、償還期限も10年以内と比較的長めです。
住居確保給付金
住居確保給付金は、失業や減収によって困窮した際に、家賃の一部を原則3ヶ月間(最長9ヶ月間)補助してもらえる給付制度です。
給付の条件は、次のように定められています。
| 給付対象 | 以下の条件に該当する世帯が対象。 ・主たる生計維持者が離職・廃業から2年以内である ・離職・休業などによって収入が減った世帯 ・住居を失うおそれがある世帯 |
|---|---|
| 支給上限額 | 住まいの市区町村や世帯人数によって異なる。 東京都特別区の場合(1ヶ月当たり) 世帯人数1人:5万3700円 世帯人数2人:6万4000円 世帯人数3人:6万9800円 |
参考:「厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ウェブサイト | 住居確保給付金:制度概要」
上記の3つとは異なり給付制度となるため、返済の必要はありません。
借金を返せないとどうなる?
万が一、借金の返済が困難になった場合、どのような影響が生じるのでしょうか。
滞納の期間や状況によってリスクの内容は異なりますが、放置を続けることで生活への支障が徐々に大きくなる可能性があります。
| 滞納期間 | リスク |
|---|---|
| 翌日~ | 督促状が届く・遅延損害金の加算 |
| 2~3ヶ月 | ブラックリストに載る |
| 2、3ヶ月以上 | 一括請求の通知が届く |
| 一括請求を無視した場合 | 裁判所から支払督促や訴状が届く |
| 訴訟に対応しなかった場合 | 差し押さえの強制執行 |
それぞれのリスクについて、詳しく解説していきましょう。
【支払日翌日〜】遅延損害金の加算・督促が始まる
返済期日の翌日から、電話やメール、郵便による督促が始まります。
加えて、返済期日から1日でも遅れると、遅延金損害金が発生します。
遅延損害金とは、支払いが遅れた際の損害賠償金の一種で、次の計算式によって算出されます。
返済額(借金残高) × 遅延損害金利率 ÷ 365(日) × 延滞日数(返済期日の翌日から延滞が解消された日までの日数)
遅延損害金の上限利率は、年20%と定められています。
借金残高が10万円、遅延損害金利率が年20%、滞納日数が30日とすると、次のように計算されます。
10万円 × 20% ÷ 365日 × 30日 =1643円
上記の条件の場合、遅延損害金は1643円となります。
【滞納2ヶ月〜】ブラックリストに載る
滞納して2ヶ月以上が経過すると、信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。いわゆる「ブラックリストに載る」といわれる状態です。
信用情報機関とは、クレジットカードや各種ローンの申込・契約・利用・返済履歴などがまとめられた信用情報を管理している組織のこと。
金融機関は新規契約や更新のための審査を行う際に、契約者の信用情報を確認します。
事故情報が登録されていると「返済能力に問題がある」とみなされてしまい、クレジットカードの利用や新規作成、新規での借入ができなくなる可能性が高いといえます。
滞納に関する事故情報の登録期間は、原則として滞納が解消されてから5年程度といわれています。
【滞納2、3ヶ月〜】一括請求の通知が届く
滞納が2~3ヶ月以上続くと、債権者やその代理人弁護士から一括請求の通知が内容証明郵便で届きます。
一括請求とは、滞納額だけでなく、借金残高のすべてに遅延損害金を加算した金額を一括で支払うことを求めるものです。
一括請求が行われるのは、債務者(お金を借りた人)が「期限の利益」を喪失してしまうからです。
「期限の利益」とは、契約によって定められた期限までは返済をしなくてもいいという債務者の権利のことです。
「期限の利益」を失うことで、実質的に返済期限が消滅するため、債権者は一括請求を行うことができるのです。
一括請求を放置すると、裁判所から支払督促や訴状が届く
一括請求の通知に応じず、無視した状態が続くと、債務者が裁判所に申立てを行うケースがあります。
申立てが行われた場合、裁判所からの「支払督促」や「訴状」が届きます。
「支払督促」とは、借金の滞納などがあった場合に、申立人(債権者)側の申立てに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方(債務者)に支払いを命じる手続きのことです。
「支払督促」や「訴状」が届いてから2週間以内に裁判所に異議申立てを行うことで、差し押さえの執行を止めることができます。
ただし、異議申し立てを行えば自動的に請求が退けられるわけではありません。
多くの場合、債権者側が十分な証拠をもとに請求しているため、最終的に支払い義務が認められる可能性が高いのが実情です。
訴訟に対応しないと、強制執行で財産が差し押さえられる
支払督促や訴状が届いてから2週間以内に裁判所に異議申立てを行わなかった場合、裁判所からの「仮執行宣言付支払督促」という書類が特別送達で届きます。
仮執行宣言付支払督促は、財産や給与が強制的に差し押さえられることを意味します。
差し押さえの対象としては、給与や現金、債務者名義の預貯金、自動車、土地、建物などが挙げられます。
給与はもっとも差し押さえられる可能性の高い財産といえますが、全額が回収されてしまうわけではありません。「手取り給与の4分の1」もしくは「33万円を超過した分」が、差し押さえの対象となります。

給与の差し押さえが行われる場合は、債権者から勤務先に連絡がいくため、借金を滞納していることが同僚に知られてしまう可能性があります。
借金が返せなくなったときにやってはいけない行動
仮に借金の返済ができなくなった場合、次の行動は避けたほうがいいでしょう。
それぞれのNG行動について、詳しく解説していきましょう。
督促などの通達を無視する
滞納時にもっとも避けるべきは、届いている督促などの書面を無視し続けることです。
先述したとおり、無視をしても督促は止まらないだけでなく、さらに状況が悪化していきます。
遅延損害金は日を追うごとに増えていき、滞納してから2ヶ月以上が経過すると一括請求されるリスクもあります。
最悪の場合、給与や財産などを差し押さえられてしまう可能性もあるのです。
一括請求や差し押さえを避けるためにも、返済が困難だと感じ始めた時点で、債権者への相談や債務整理などに動き出すことが重要です。
返済のためにさらに借金をする
返済のための費用を捻出できないからといって、別の金融機関から新たに借入を行うのもNGです。
新たに借金をして従来の借金を返済する「自転車操業」は、一時的に返済を継続できるかもしれませんが、借入残高を増やすことにつながりかねません。
また、1人が融資を受けられる金額は「年収の3分の1」までと、「総量規制」という制度で定められています。
複数社からの借入を合計して「年収の3分の1」以上となれば、それ以上の融資は受けられません。
なお、2ヶ月以上滞納をするとブラックリストに載り、新規契約の審査に通らなくなるため、借入によるお金の工面もできなくなります。
クレジットカードの現金化
クレジットカードの現金化とは、クレジットカードを利用して購入したものを販売し、現金を手にすることです。
そもそもクレジットカードの現金化は、クレジットカード会社の規約に反する行為として禁止されています。
現金化が発覚すると、強制退会や残高の一括請求などの措置が取られるリスクがあるので、返済のためにいますぐお金が必要だったとしても、絶対に避けるべき行為だといえます。
借金が返済できないときは弁護士・司法書士事務所に相談
どうしても借金返済の目途が立たないというときは、弁護士・司法書士事務所への相談や依頼を検討しましょう。
専門家に相談・依頼することで、次のような効果を得ることができます。
正しい解決方法を見つけられる
債務整理を検討する際、「任意整理」「個人再生」「自己破産」のうち、最も適した方法を個人で判断するのは容易ではありません。
弁護士や司法書士は債務整理に関する法律や実務に精通しており、借金残高や収支の状況、今後の生活設計などを総合的に踏まえたうえで、適切な選択を助言・提案しています。
また、弁護士・司法書士には守秘義務があり、相談内容が外部に漏れることはありません。
借金に関する不安や悩みを安心してお話いただき、率直な気持ちをお聞かせいただくことが、より良い解決につながります。
任意整理の最中に生じる不安や疑問についても、状況に応じたアドバイスやサポートを提供し、依頼者の方が納得したうえで進められるよう、対応します。
債権者からの督促が止まる
弁護士や司法書士に債務整理の手続きを依頼すると、最短即日で債権者からの督促を止めることができます。
弁護士・司法書士から債権者に対して、「受任通知」が送付されるからです。
「受任通知」とは、弁護士や司法書士が債務者に代わって債務整理の手続きを行うことを通達するための書面です。
「受任通知」が送付された時点から債務整理の手続きが完了するまで、債権者は督促をストップしなければいけないと、貸金業法第21条で定められています。
督促が止まるということは、返済も一時的にストップすることになるため、その間に生活を立て直したり、返済するための費用を準備したりすることができるでしょう。
弁護士・司法書士に支払う費用も、手続き中に積み立てることができます。
面倒な手続きや交渉を代行・サポートしてくれる
弁護士や司法書士に依頼することで、「任意整理」の交渉や「個人再生」「自己破産」に必要な裁判所への申立てなどをスムーズに進めることができます。
「任意整理」を行う場合は、金融業者との直接交渉や正確な返済額を導き出す計算など、手間のかかる作業が多く発生します。
法律の知識と債務整理の経験が豊富な弁護士・司法書士に依頼することで、一連の作業を委ねられるだけでなく、個人で交渉するより有利な条件で和解できる可能性が高くなります。
「個人再生」や「自己破産」では裁判所を介する必要があり、申立てから必要書類の準備、債権者とのやり取りなど、手続きが複雑です。
弁護士や司法書士であれば、それらの手続きの代行もしくはサポートをしてくれるので、専門知識がなくても手続きを進めることができます。
当事務所にご相談いただければ、現在の収支状況や借金残高をヒアリングしたうえで、最適な債務整理方法をご提案いたします。
ご相談は何度でも無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。