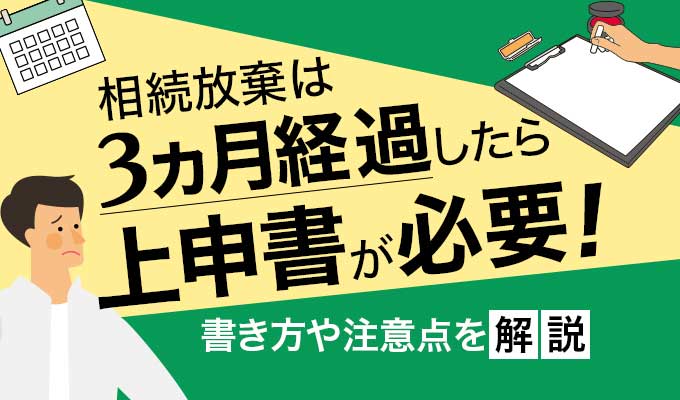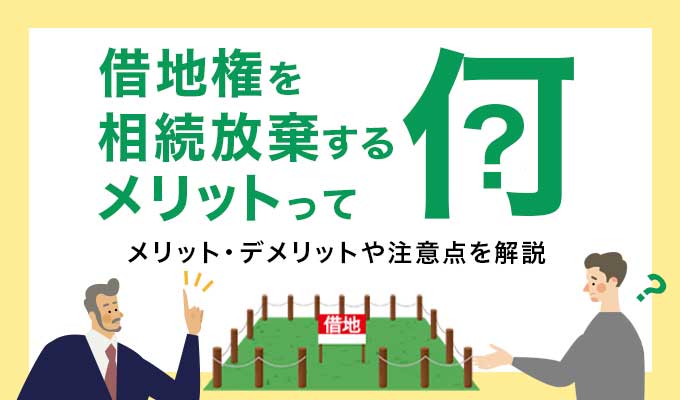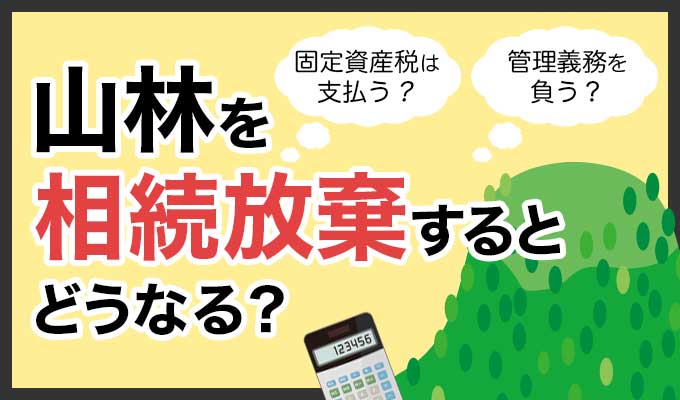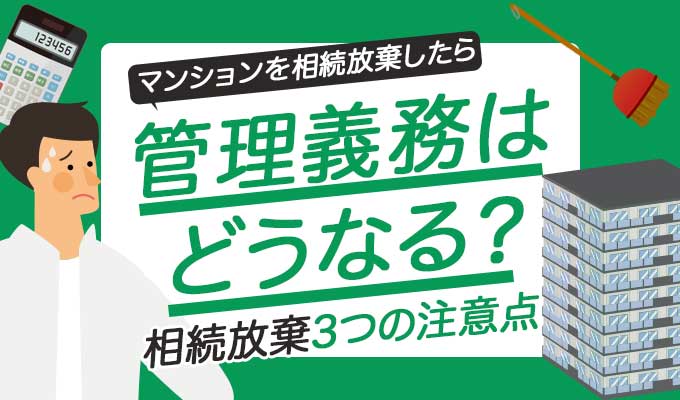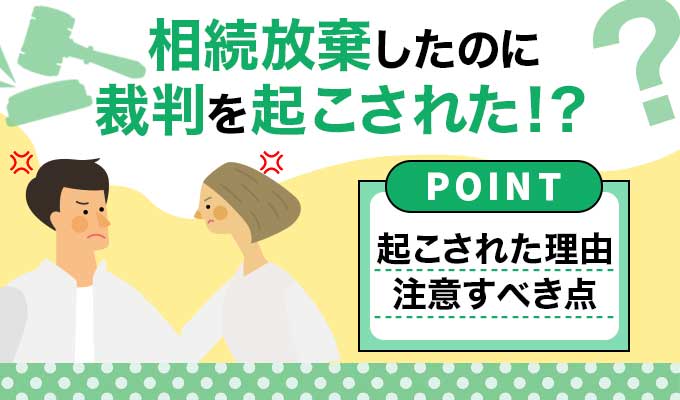相続放棄
孤独死の相続放棄はどうする?対処すべきことや注意点を徹底解説

長い間連絡をとっていなかった家族が孤独死したとの連絡を受けた場合、まず何からすべきなのか、わからない方も多いのではないでしょうか。
その際に気をつけてほしいのは、家族構成や財産状況が何もわからなくても、そのまま放っておくと孤独死した方の財産を相続してしまうことです。
借金がある場合は借金も相続することになる可能性があります。
そのため、場合によっては相続放棄をご検討ください。
また、疎遠だったにもかかわらず、遺品整理の義務や葬儀を開催する義務などが課されてしまうかも、気になるところだと思います。
この記事では、孤独死の連絡を受けた際にするべきことや、相続放棄をする際の対処法や注意点について、わかりやすく解説していきます。
目次
孤独死の連絡を受けたらまずは身元確認から
警察や役所などから「家族が孤独死した」と連絡を受けたら、まず身元確認を行いましょう。
孤独死の場合、誰にも気づかれずに家の中で倒れてしまい、長期間にわたって遺体が放置されていたため腐敗によって遺体が損傷し、身内でも本当に自分の家族なのかがわからないこともあります。
そのため、まず亡くなったのが本当に自分の家族なのかをしっかり確認することが重要です。
孤独死するような状況の場合、警察や役所、親戚や近所の人などから連絡を受けることで、家族の孤独死を知ることになるでしょう。
突然の連絡に気が動転してしまうかもしれませんが、 孤独死の連絡を受けたら、次の事項を正確に把握するようにしてください。
- なぜ自分に連絡がきたのか(ほかの相続人には連絡がつかなかったのか)
- 亡くなったのは本当に自分の家族なのか(名前、亡くなっていた場所、勤務先など)
- 現在の状況と今後の流れについて
今後の対応は、ケースバイケースですが、基本的には警察や役所の言うとおりに手続きを進めることになるでしょう。
身元確認のうえ、亡くなったのが自分の家族であることが判明した場合、警察や役所の指示に従って手続きを進めるとともに、相続や相続放棄のことも考えていくことになります。
孤独死の相続放棄をする際に対処すべきこと
故人の身元が判明し、相続や相続放棄を検討する際は、以下の3つのことを行いましょう。
| 1.自分が本当に相続人なのか調べるため相続人調査をする 2.相続放棄をすべきか判断するために相続財産調査をする 3.相続放棄をする場合は期限内に裁判所で手続きをする |
一つずつ解説していきます。
1.自分が本当に相続人なのか調べるため相続人調査をする
孤独死をしていたのが疎遠だった家族だとわかったら、自分に相続をする権利があるかどうかご確認ください。
ほかに相続人がいる場合などは、家族であっても相続権が回ってきていないことがあります。
その場合は、相続放棄をする必要はありません。
自分よりも順位が上の相続人がいると、相続権が回ってきていないケースもあります。
警察や役所は、連絡の取れる親族に優先的に連絡しているだけで、必ずしも相続人に対して連絡してくるわけではありません。
そのため、相続について考える際は、必ず相続人調査を行いましょう。
その際は、親戚や知人などから聞いた情報でだけ判断するのではなく、故人の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本)などを取得して、正確におこなうようにしてください。
2024年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地以外の役所でも、戸籍を取得できるようになりました。
被相続人の戸籍などを集める作業は、以前よりも進めやすくなっています。
ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本(除籍謄本)は、本来の自治体に請求する必要があり、戸籍の読み方を理解していないと、誰が相続人なのかが読み解けない場合も多いです。
自力での相続人調査は大変な労力を伴う可能性があります。
手間や時間を省くためにも、相続人調査は司法書士などの専門家のサポートを受けることをおすすめします。
自分と別に相続人がいることを知っている場合は直接連絡を取る
自分よりも先に相続すべき人がいることを知っていたり、相続人調査の結果、ほかの相続人が発覚した場合には、その相続人に連絡をとって、相続放棄をするかどうかの確認をする必要があります。
先順位の相続人がいるなら、その人が相続放棄しない限り、自分に相続する権利が回ってくることはありません。
法定相続人および相続順位は以下のように定められています。
| 相続順位 | 法定相続人 |
|---|---|
| 第1順位 | 被相続人の子、孫(直系卑属) |
| 第2順位 | 被相続人の父母、祖父母(直系尊属) |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
※被相続人の配偶者は順位に関係なく常に相続人になります。
たとえば、自分の兄が孤独死していたものの、すでに両親が他界していることから、弟である自分のところに警察から連絡が入った場合を想定します。
このケースでは、孤独死した兄に離婚歴があり、別れた妻との間に子どもがいた場合には、弟である自分の前に、その子どもが相続する権利を持つことになります。
その子どもが相続放棄をしたら弟に相続する権利が回ってきます。
このように、たとえ家族であっても、そもそも相続する権利が回ってきていないケースもあります。
自分よりも先に相続すべき人がいたり、相続人調査の結果ほかの相続人が発覚したりした場合には、その相続人と直接連絡を取るのが良いでしょう。
2.相続放棄をすべきか判断するために相続財産調査をする
家族が孤独死したら、相続財産調査もしっかりおこなうようにしましょう。
預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産まで正確に調べることで、相続放棄の判断を適切にできるようになります。
生前、消費者金融からお金を借りていたとしても、いざ財産調査をしてみたら、借金以上に資産を蓄えていたことがわかるケースもあります。
この場合、そのまま遺産を相続したうえで、相続財産の中から借金の返済をおこなったほうが、金銭的なメリットがあるでしょう。
長い間被相続人と疎遠で、「これ以上かかわりたくない」という理由だけで相続放棄をすると、金銭的に損をしてしまうこともあるでしょう。
相続放棄の撤回はできず、基本的に取り消しも認められていません。
相続放棄で受け取れるはずの財産を手放してしまわないためにも、相続財産調査を入念におこなってから判断することをおすすめします。
なお、相続財産の調査は、預貯金口座や各種契約書、定期的に届く書面や役所関係の書面などから、一つひとつ丁寧に調査をしていくことになります。
預貯金、不動産、高価な衣類、貴金属、有価証券、暗号資産などのプラスの財産だけではなく、金融機関からの借入れ、滞納している税金、医療費、家賃、携帯代などのマイナスの財産まで正確に把握するのは、非常に大変です。
相続放棄の手間を省きたいのであれば、相続財産の調査から、司法書士などの専門家への依頼を検討するのが良いでしょう
3.相続放棄をする場合は期限内に裁判所で手続きをする
相続人調査および相続財産調査をおこなった結果、相続放棄をすることになった場合、相続放棄の期限内に、家庭裁判所に対して必要書類を提出する必要があります。
相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内です(熟慮期間と言います)。
3ヶ月の期限がスタートする日は「被相続人の死亡日」となるのが一般的ですが、孤独死の場合には、「警察や役所などから連絡を受けて、家族の孤独死を知った日」になるケースが多いです。
3ヶ月と聞くと時間があるように感じるかもしれませんが、相続人が複数いたり、不動産や株、暗号通貨など財産の構成が複雑だったりすると期限内に手続きを進めることが難しいケースもあります。
もし、3ヶ月では財産調査が終わらなそうであれば、家庭裁判所に申述して、熟慮期間を1〜3ヶ月程度伸長(延長)してもらえることもあります。
裁判所に申請することなく熟慮期間を過ぎてしまうと、相続放棄が認められなくなってしまうので、時間に余裕を持って財産調査や提出書類の収集をおこなってください。
なお、相続放棄の申述は、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に対しておこないます。
「被相続人の最後の住所地」は住民票などで確認が可能です。
相続や遺言の
無料相談受付中!
-
電話での無料相談はこちら
0120-243-032
受付時間 9:00~18:00
(土日祝日の相談は要予約) -
メールでの
無料相談はこちら

孤独死で親族全員が相続放棄をしたらどうなる?
たとえば、孤独死した方が未婚で子どもがおらず、両親もすでに他界していた状況で、唯一の兄弟が相続放棄した場合には、被相続人の財産を相続する人がいなくなります。
この場合、受遺者や特別縁故者など、被相続人と関係のある人に対して相続財産が分配されることになります。
それでも財産を受け継ぐ人が見当たらない場合には、最終的には国に財産が引き渡されるでしょう。
ここからは、受遺者や特別縁故者などに財産を引き渡す「相続財産清算人」の役割や、相続財産の国庫帰属の流れについて解説していきます。
相続財産清算人により受遺者や特別縁故者などに財産が渡る
相続放棄により遺産を相続する人がいなくなった際、遺言によって財産を受け取れる受遺者や、内縁の妻など、被相続人と特別な関係にあった特別縁故者がいる場合には、相続財産清算人により、受遺者や特別縁故者などに遺産が引き継がれることになります。
相続財産清算人とは、相続財産の管理・処分をおこなう人のことを指します。
受遺者や特別縁故者などの利害関係人、もしくは検察官が申し立てることで、家庭裁判所に選任してもらうのです。
なお、家庭裁判所から「債権申出の公告」がされると、受遺者は、自分に相続財産を受け取る権利があることについて届出をおこなう必要があります。届出期間は、多くの場合2ヶ月以上の期間が定められます。
また、特別縁故者が相続財産を引き継ぐケースでは、相続人の不存在が確定してから、3ヶ月以内に財産分与の申し立てをしなければなりません。
このように、相続する人がいなくなった場合には、相続財産清算人によって、受遺者や特別縁故者に対して、財産の分配がおこなわれます。
最終的に残った財産は国庫に帰属する
相続財産清算人の調査の結果、法定相続人、受遺者、特別縁故者がいないことがわかると、遺産は国庫に帰属、つまり国に対して引き渡されることになります。
相続財産清算人は、家庭裁判所の決定により、相続財産の中から自身の報酬を付与してもらいます。そのうえで、相続財産が残ってしまった場合には、残余財産の国庫引継手続きをおこなうことになります。
引継手続きの方法は、財産の種類によって異なります。たとえば、不動産であれば、登記名義を変更することで引き継ぎをおこなうケースもありますが、場合によっては、現金化されてから国庫に納められるケースもあります。
家族の孤独死で相続放棄をする際の注意点
孤独死した家族の財産を相続放棄をする場合、次の3点に注意してください。
| 1.遺品整理の義務はないが対応せざるを得ない場合は自腹でおこなう 2.賃貸借契約の保証人になっていると原状回復費用を請求される 3.遺体・遺骨の引取り義務や葬儀の開催義務はない |
以下、それぞれ詳しく解説していきます。
1.遺品整理の義務はないが対応せざるを得ない場合は自腹でおこなう
孤独死した家族の遺品整理をせざるを得ない状況であれば、遺品整理にかかる費用は自腹でおこなうようにしてください。
遺品整理業者依頼にかかる費用や家具の処分費用などを相続財産の中から支払ってしまうと、単純承認とみなされ、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
単純承認とは、被相続人の相続財産を無条件ですべて相続することを指します。
たとえば、相続放棄をしているにもかかわらず、遺品を整理してしまったり、価値のある財産を処分してしまったりすると、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます(民法921条1号)。
家族が孤独死した場合でも、相続放棄をしているのであれば、遺品整理の義務を負うことはありません。そのため、亡くなった家族の遺品をそのまま放置しておいても問題はありません。
一方で、賃貸物件で孤独死した場合、大家さんから「せめて遺品だけでも持ち帰ってくれ」と頼まれてしまうこともあると思います。
もし、どうしても遺品整理の対応をせざるを得ない状況であれば、遺品整理にかかる費用は自腹でおこなうのが望ましいでしょう。
ただし、たとえ自腹で遺品整理をおこなったとしても、価値のある財産を処分したり譲り受けたりした場合、単純承認とみなされ相続放棄ができなくなるおそれがあります。
大家さんの頼みを断るのは心苦しいかもしれませんが、ほかの相続人が相続するか、もしくは相続財産清算人に遺品整理をしてもらうまでは、相続財産には一切手をつけないようにしましょう。
【参考】民法|e-Gov法令検索
2.賃貸借契約の保証人になっていると原状回復費用を請求される
相続人が、孤独死した方の賃貸借契約における連帯保証人になっている場合、相続放棄しても原状回復費用(退去費用)を支払う義務が残ってしまう可能性があります。
賃貸借契約における連帯保証人としての地位は、連帯保証人と債権者との間で発生します。このケースでいうと、相続人と大家さんとの間で連帯保証債務が発生していることになります。
連帯保証債務は、被相続人のマイナスの財産ではなく、相続人自身が負っている債務とみなされるため、相続放棄で支払いを免れられないのです。
そのため、大家さんから原状回復費用を請求されてしまったら、支払いに応じる必要が生じます。
なお、原状回復費として請求される可能性のあるものは、次のとおりです。
| ● 明渡しまでの家賃(それぞれの賃貸借契約書に基づき計算されます) ● 集合住宅における共益費・管理費 ● 原状回復費用(特殊清掃費を含む) ● 内装交換費用(畳・カーペット・クロス) など |
3.遺体・遺骨の引取り義務や葬儀の開催義務はない
相続人だからといって、遺体・遺骨の引取義務や葬儀の開催義務はありません。
被相続人と同居していたり、仲が良かったりした場合には、遺体・遺骨を引き取り、葬儀をおこなうこともあるでしょう。
しかし、遺体・遺骨の引取義務や葬儀の開催は、法律上要求される義務ではありません。
そのため、身内の孤独死であったとしても、生前疎遠で連絡をとっていなかったなどの事情があるなら、引き取りを拒めます。
葬儀についても、相続人に開催義務があるわけではありません。
葬儀を行う際は葬儀代を相続財産から支払っても単純承認にはならないケースがほとんどですが、葬儀代が高額すぎる場合など、葬儀の規模によっては、相続放棄が認められない可能性もあります。
葬儀の規模は、宗派や地域などによってさまざまです。とくに会社の代表者や知名度のある人が葬儀をおこなう場合には、参列者の多さも相まってかなり豪華な葬儀になるケースもあるでしょう。
もし、一般的にみて、身分相応の範囲を越えるような豪華な葬儀をおこなってしまうと、その適切な範囲を越えた部分については「相続財産を処分した」とみなされ、単純承認に該当し、相続放棄が認められなくなってしまう可能性があるのです。
相続人が自腹で葬儀をおこなうのであればよいですが、相続放棄をしたうえで葬儀をおこなうのであれば、葬儀の規模は必要以上に華美にしすぎないように注意してください。
孤独死の相続放棄で兄弟がいる場合はまとめて手続きをするとよい
家族が孤独死して、相続人全員が相続放棄を希望している場合には、まとめて手続きするとスムーズです。
前述したように、相続人には相続の順番が決められており、順位が上の人から順番に権利が回ってきます。
たとえば、孤独死した方に子どもが複数人いた場合、その子どもは全員第1順位の相続人なので、まとめて相続放棄をおこなえます。
後順位の相続人は、先順位の相続人がいない、もしくは相続放棄した場合ではないと、相続する権利が回ってきません。
そのため、まだ自分に相続する権利が回ってきていない状況では、相続放棄の手続きを進めることもできず、相続順位が異なる相続人が同時に相続放棄はできないことになります。
この点、親族まとめて相続放棄をおこなえば、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本など、兄弟で共通して必要な提出書類は1通用意すればよくなったり、専門家に支払う費用を割り引いてもらえたりする可能性があります。
相続人同士で、相続放棄の話し合いもおこなうので、相続人の間でのトラブルを避けることにも繋がります。
家族が孤独死して、相続人全員が相続放棄を希望している場合には、相続人全員まとめて手続きすることをおすすめします。
まとめ
警察や役所から連絡があり、孤独死が判明した場合には、まずは本当に自分の家族が亡くなったのかどうかを冷静に確認してください。
そのうえで、相続人調査や相続財産調査を入念におこない、相続するか相続放棄をするかの判断をくだすことになるでしょう。
もし、相続放棄するなら、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内の熟慮期間に手続きをおこなう必要があります。そのため、必要書類の準備や財産調査をスムーズにおこなう必要があるでしょう。
家族が孤独死をしたケースでの相続放棄は、相続人調査や相続財産調査、さらには相続放棄の手続きと、やることが多いため、専門家に依頼して進めることをオススメします。
専門家に依頼すれば、ご自身の負担を大きく軽減することが可能です。
司法書士法人みつ葉グループでは、相続放棄の無料相談を実施中です。
家族が孤独死をしていることがわかり、相続や今後の対応で迷ったら、みつ葉の司法書士までお問い合せください。
カテゴリ