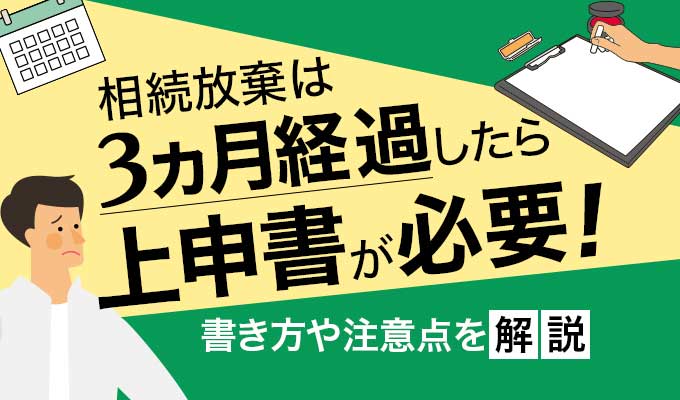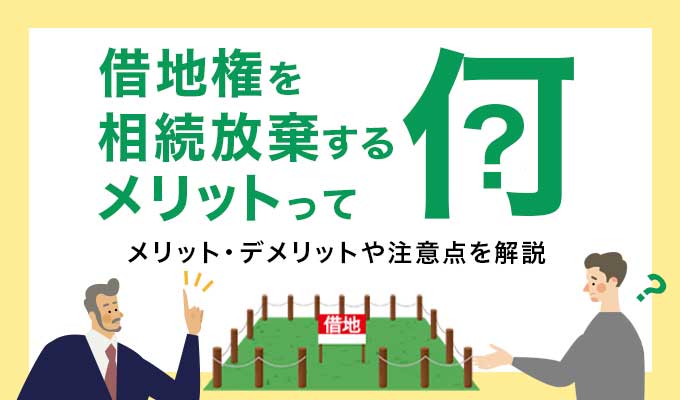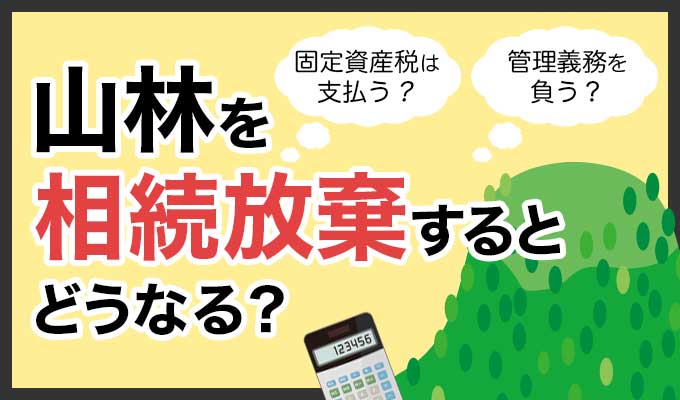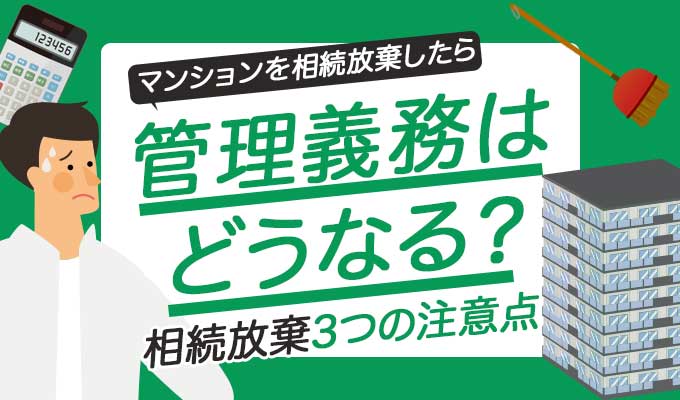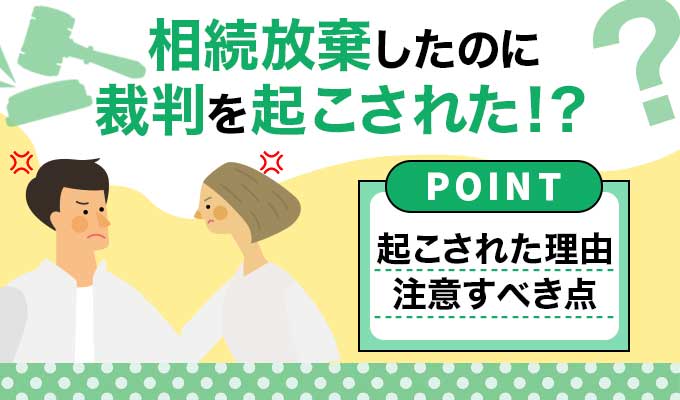相続放棄
連帯保証人は相続放棄できる?できない?注意点や対処法を解説

亡くなった家族の遺品整理で多額の借金が発覚した場合、その借金を相続しないためにも、相続放棄を検討することとなるでしょう。
もし、亡くなった家族が生前に誰かの連帯保証人となっていた場合、相続放棄で連帯保証人としての地位も免れることはできるのでしょうか。
また、相続人自身が、亡くなった家族の連帯保証人となっていた場合、相続放棄で支払義務がなくなるのかも気になるところだと思います。
この記事では、連帯保証人の相続放棄について、「被相続人が連帯保証人だった場合」と「相続人自身が連帯保証人だった場合」の2つのケースに分けて、対処法や注意点をわかりやすく解説していきます。
目次
連帯保証人の相続放棄はどうなる?
連帯保証人の相続放棄については、「被相続人が連帯保証人だった場合」と「相続人自身が連帯保証人だった場合」の2つに分けて考える必要があります。
この2つのケースで、相続放棄をするとどうなるのか、順番に解説します。
被相続人が連帯保証人の場合の相続放棄
被相続人が第三者の連帯保証人となっていた場合、相続放棄をすれば、相続人が連帯保証人として返済する義務は無くなります。
被相続人の連帯保証債務は、借金などと同じマイナスの財産に該当するためです。
相続をすると、連帯保証人としての支払い義務も相続することになってしまいますので、被相続人が連帯保証人になっていた場合は十分にご注意ください。
相続人自身が連帯保証人の場合の相続放棄
被相続人の借金の連帯保証人に相続人がなっている場合、相続放棄をしても連帯保証債務は残ります。
この場合、相続放棄をすることで借金自体の返済義務を相続することはなくなりますが、被相続人が生前に返済できなかった借金を、連帯保証人として代わりに請求されてしまう恐れがあります。
相続に関係なく、元から連帯保証人だからです。
この際、「相続放棄をしたから」という理由で支払いを拒否することは認められませんのでご注意ください。
この連帯保証人としての責任は借金を完済するまで継続します。
連帯保証人として支払いを求められた場合の対処法
被相続人が連帯保証人になっていたことを知らずに相続してしまい、後から借金の返済を求められてしまった場合、元から被相続人の借金の連帯保証人で、被相続人の死後、返済を求められてしまった場合の5つの対処法を紹介します。
| 対処法1.連帯保証債務を全額負担する 対処法2.債権者と交渉して減額してもらう 対処法3.任意整理によって返済負担を軽減する 対処法4.個人再生の申立てをおこなう 対処法5.自己破産の申立てをおこなう |
それぞれ解説していきます。
対処法1.連帯保証債務を全額負担する
一括で全額返済できるだけの資力があるのなら、まずは連帯保証債務を全額負担することを検討してみましょう。
借金額がそこまで大きくないのであれば、分割払いなどで利息を取られるよりも、すぐに全額返済したほうが負担は少ない可能性があります。
連帯保証人として全額返済する場合、本来ならほかの連帯保証人(法定相続人)が負担すべき借金額を肩代わりして返済することとなります。
借金を全額返済すると自分だけが借金を負担することになるため、ほかの相続人に比べて不平等だと感じるかもしれません。
しかし、この場合には、返済した金額の一部を、ほかの連帯保証人(法定相続人)に請求することができます(この権利を「求償権」といいます)。
何の前触れもなしにいきなり求償権を行使すると、ほかの連帯保証人(法定相続人)とトラブルになる可能性があります。
求償権を行使を予定して全額返済するなら、返済する前に他の連帯保証人(法定相続人)に通知をしておくことが望ましいでしょう。
対処法2.債権者と交渉して減額してもらう
連帯保証人として借金全額の支払いが難しいなら、債権者と交渉し、減額や返済期間延長の交渉をしてみるのもよいでしょう。
これらの交渉が必ずしもうまくいくとは限りません。しかし、債権者としても、自己破産などで借金の回収が一切できなくなるよりは、交渉に応じる方がメリットが大きいと判断してくれる可能性があります。
連帯保証債務を引き継いでしまったものの、一括で返済するだけの資力がないことをしっかりと伝えることで、金利の見直しや返済期間の延長に応じてくれる可能性があります。
この際、支払能力の有無を細かく調べられる可能性があります。とくに債権者が銀行などの金融機関である場合は、支払能力に見合わない減額請求や返済期間の延長は、交渉に応じてもらえないどころかトラブルに発展することもあります。
減額請求や返済期間の延長は、無理のない範囲でおこなうようにしましょう。
なお、交渉の際に連帯保証人の解除を求めることもできますが、債権者にはメリットがない交渉となるため、応じてもらうのは困難といえるでしょう。
対処法3.任意整理によって返済負担を軽減する
連帯保証債務額が大きく、一括での返済が難しく場合には、任意整理によって毎月の返済負担を減らすのもおすすめです。
任意整理とは、債権者と交渉をおこない、将来的に支払うべき利息などのカットや、返済回数を36〜60回(3〜5年)に延長することを求める手続きです。
任意整理が認められれば、利息が免除または減額されて返済の負担が軽減されます。
そのため、利息を含めた金額では返済が厳しいけれど、毎月継続した返済が可能であれば、相続した連帯保証債務について任意整理をすることも検討してみましょう。
対処法4.個人再生の申立てをおこなう
相続した借金額が大きく、元本が減らない任意整理では借金の返済が難しい場合には、個人再生を申し立て、元本を減額を目指しましょう。
個人再生とは、裁判所に申立てをおこない、債務の一部を分割して返済、残りの債務を免除してもらう手続きです。
個人再生の場合、裁判所から再生計画(返済計画)を認めてもらえれば、借金の元本そのものが5分の1〜10分の1に減額され、残りの債務を3年程度の分割払いで返済していくこととなります。
任意整理と違い、借金の元本自体を大幅に減らせるため、返済負担を大幅に軽減できることが大きなメリットです。
対処法5.自己破産の申立てをおこなう
相続した借金額が大きく、自身の経済状況から考えて返済困難な状況に陥っている場合には、自己破産で借金をゼロにすることをおすすめします。
自己破産とは、裁判所に申立てをおこない、現在の全財産を債権者に分配、残りの債務全額を免除してもらう手続きです。
税金や養育費などの一部の債務を除き、ほとんどすべての債務をゼロにできるため、返済困難な状況に陥っている場合には有効な債務整理の方法といえるでしょう。
ただし、持ち家や車、高価な貴金属など財産価値のあるものは、換価処分の対象として没収されてしまうなど、自己破産をすることのデメリットもありますので、事前に把握しましょう。
相続や遺言の
無料相談受付中!
-
電話での無料相談はこちら
0120-243-032
受付時間 9:00~18:00
(土日祝日の相談は要予約) -
メールでの
無料相談はこちら

被相続人が連帯保証人の際は限定承認という方法もある
被相続人が連帯保証人だった場合の選択肢には、相続放棄のほかに限定承認もあります。
限定承認とは、相続するもののマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、相続するマイナスの財産はプラスの財産を上限とするというものです。
たとえば、被相続人の預金が100万円あり、後から連帯保証人として150万円を請求されてしまった場合、100万円までは連帯保証人として支払う義務がありますが、50万円は支払う義務がなくなるというものです。
限定承認を選択すれば、連帯保証人として返済を求められた際に、相続したプラスの財産は失うかもしれないものの、借金を抱え込む結果は避けることができます。
限定承認が適しているのは、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いかよくわからない場合や、連帯保証債務を一部(あるいは全額)返済してでも引き継ぎたい財産がある場合です。
限定承認は後から行うことはできず、相続または相続放棄と同じように3ヶ月の熟慮期間内に手続きをおこなわなければなりません。
また、手続き自体も相続放棄より複雑で、相続人全員の同意がなければ手続きをおこなえない点には注意が必要です。
被相続人が連帯保証人の際に相続放棄をする注意点
被相続人が連帯保証人だった場合の相続放棄においては、以下の点に注意しましょう。
| 注意点1.連帯保証人の地位のみを相続放棄することはできない 注意点2.相続放棄すると連帯保証債務は次順位の相続人が負う 注意点3.必ずしも連帯保証債務の支払義務があるとは限らない 注意点4.単純承認に気をつけなければならない |
それぞれの注意点について、詳しく解説していきます。
注意点1.連帯保証人の地位のみを相続放棄することはできない
連帯保証人の地位などのマイナスの財産のみを相続放棄することはできません。
相続放棄するのであれば、プラスの資産も含めたすべての財産を放棄することになります。
相続放棄は、被相続人の相続財産を一切引き継がないことにする手続きです。
相続財産の中の一部を選択することはできません。
被相続人が連帯保証人だったとわかると「相続放棄をしたほうが良い」と考えると思いますが、プラスの財産が多い場合には、相続放棄をすることでプラスの財産を一切相続できなくなり、損をする結果になるかもしれませんので、ご注意ください。
注意点2.相続放棄すると連帯保証債務は次順位の相続人が負う
自身が相続放棄することで、連帯保証債務は次順位の相続人へと移ります。
相続放棄することでほかの相続人に迷惑をかけないためにも、事前に相続人同士で話し合っておきましょう。
相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったと扱われるため、相続する権利は次順位の相続人に移ります。
相続放棄をすると、被相続人の連帯保証債務も次順位の相続人へと引き継がれることとなり、その相続人に迷惑をかけてしまう可能性があります。
民法では相続する順番について、以下のように規定しています。
【相続順位】
| 第1順位:被相続人の子、孫(直系卑属) 第2順位:被相続人の父母、祖父母(直系尊属) 第3順位:被相続人の兄弟姉妹 ※被相続人の配偶者は、順位に関係なく常に相続人となる。 |
たとえば、連帯保証債務を抱えた夫が亡くなり、妻と第1順位の相続人である子どもが相続放棄したケースを想定してみましょう。
この場合、連帯保証債務は、第2順位の相続人である被相続人の両親に引き継がれます。被相続人の両親には連帯保証債務が残され、相続・相続放棄の判断や手続きにも余計な手間をかけてしまうのです。
このように、自身が相続放棄をすることで、ほかの相続人や次順位の相続人が負担を負う可能性が高まります。相続放棄する際には、事前に相続人同士で話し合っておきましょう。
なお、財産調査の結果、プラスの財産がほとんどないケースであれば、相続人全員で相続放棄することで、相続人全員が被相続人の連帯保証債務を相続せずに済みます。
注意点3.必ずしも連帯保証債務の支払義務があるとは限らない
被相続人の連帯保証人の地位を相続したからといって、必ずしも連帯保証債務の支払義務があるとは限りません。
焦って相続放棄をするとプラスの財産まで手放すことになってしまうため、注意が必要です。
主債務者が確実に返済をおこなっているのであれば、そもそも連帯保証人が借金を返済する義務を負いません。
当然、連帯保証人の地位を引き継いだ相続人にも、返済義務は発生しません。
相続財産を調査している最中に、連帯保証人になったことがわかる書類を見つけ、慌てて相続放棄をしてしまうと、本来であれば相続できる財産まで放棄してしまうこともあるでしょう。
被相続人が連帯保証人の場合に相続放棄するかどうかの判断は、主債務者が毎月確実に借金の返済をしているかどうかも含めて、慎重に判断しましょう。
注意点4.単純承認に気をつける
相続放棄を検討しているのであれば、手続き前に「単純承認」に該当することがないよう、注意しましょう。
相続放棄前に相続財産の処分をしたり、相続放棄の期限を過ぎてしまったりすると、被相続人の相続財産を無条件ですべて相続することを意味する単純承認に該当し、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。
たとえば、相続放棄をする前に遺品を整理してしまったり、価値のある財産を処分してしまったりするケースが単純承認に該当します。相続財産の中から連帯保証債務の返済をすることも単純承認に該当するため、相続放棄を検討しているのであれば、相続財産には一切手をつけずにしておきましょう。
まとめ
連帯保証人の相続放棄については、「被相続人が連帯保証人だった場合」と「相続人自身が連帯保証人だった場合」の2つのケースがあります。
被相続人が連帯保証人だった場合、相続放棄をすることで借金の返済義務を免れます。
一方で相続人自身が連帯保証人だった場合、相続放棄をしても借金の返済義務を免れることはできません。
もし、被相続人が連帯保証人だった場合に相続放棄を検討しているのであれば、相続財産調査をしっかりとおこなった上で、金銭的に損をしないような選択をすることが大切です。
3ヶ月以内という期限はあるものの、慌てて相続放棄の手続きを進めると、連帯保証債務の返済義務を負わないにもかかわらず、多額の財産を放棄してしまうことになりかねませんのでご注意ください。
相続に連帯保証人が絡んでくる場合は、相続と借金問題に精通した専門家に相談をしましょう。
司法書士みつ葉グループでは、相続も借金問題ともに力を入れて取り組んでおり、相続や相続放棄に関するアドバイス、連帯保証人として借金の返済を求められてしまった場合のサポートが可能です。
ご相談は無料です。まずはみつ葉グループの司法書士にご連絡ください。
カテゴリ