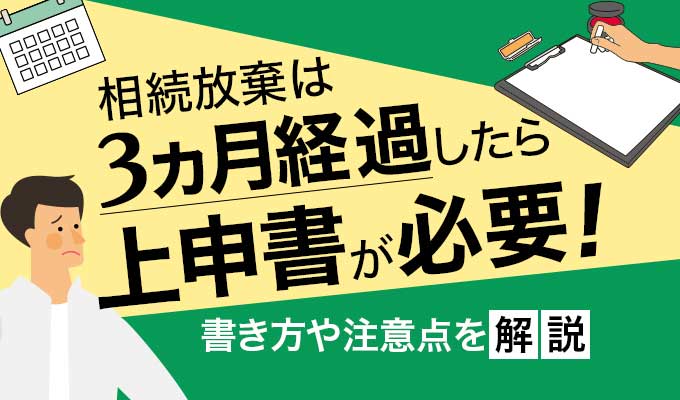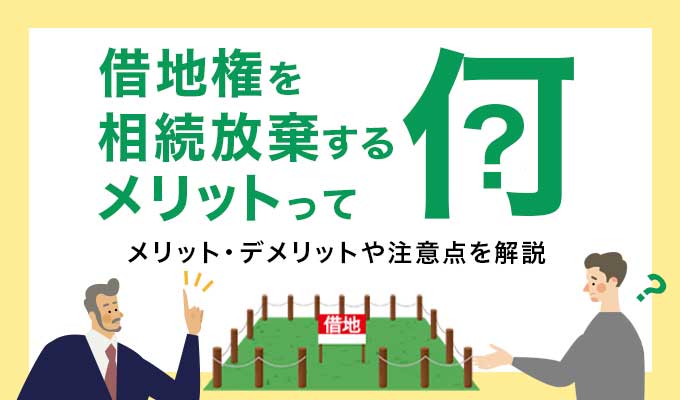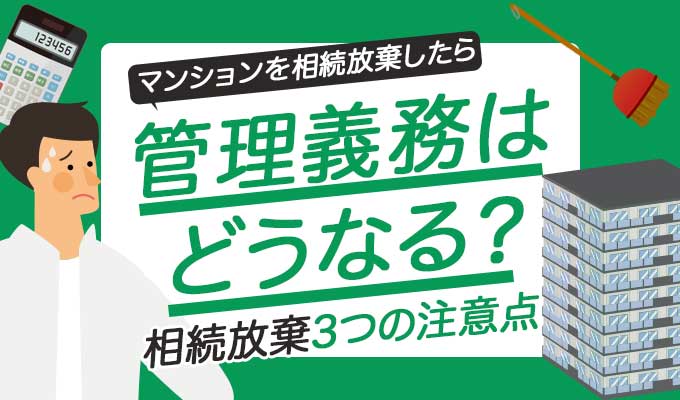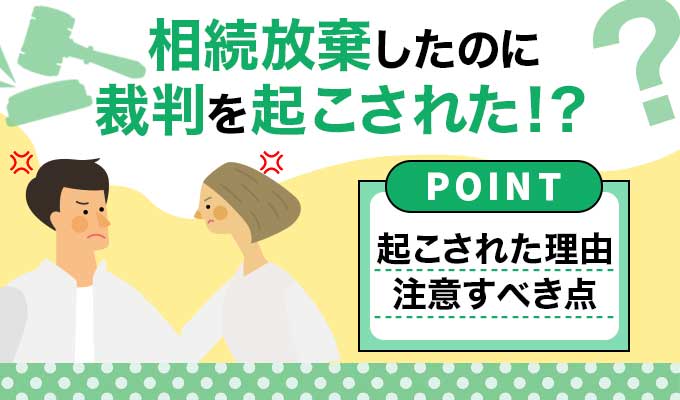相続放棄
山林を相続放棄するとどうなる?注意点や相続放棄以外の処分方法を解説
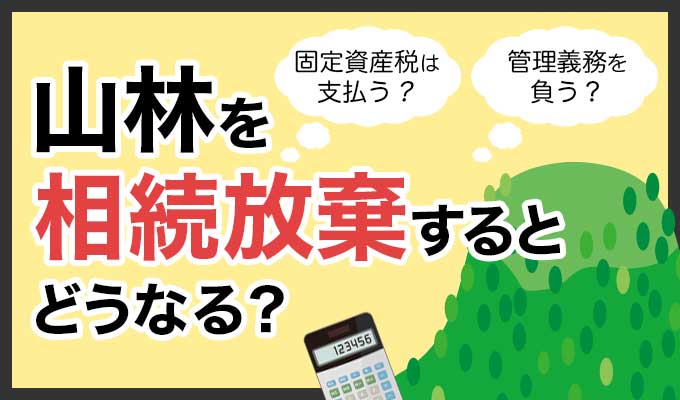
相続財産の中に山林が含まれていた場合、相続放棄で所有権を手放すことはできるのでしょうか。
相続すれば、林業を営む方に貸し出したり、レジャー施設として活用したりするなど、山林を有効活用する方法もいくつかあります。しかし、負担がかかることなので、活用するのではなく相続放棄をしたいと考える方もいるでしょう。
相続放棄をすれば所有権を手放すことは可能です。ただし、保存義務だけが残ってしまったり、タイミングによっては固定資産税の支払い義務が発生してしまったりする可能性があります。
そのため山林の相続をしたくない場合は、相続放棄、相続放棄以外の方法も含めて検討する必要があるでしょう。
この記事では、山林を相続放棄するメリットや注意点などについて、わかりやすく解説していきます。
目次
山林を相続放棄することは可能
山林を相続放棄することは可能です。
山林も相続財産の一部なので、相続放棄をして山林を引き継がない選択はできます。
一方、相続放棄せずに山林を相続することももちろん可能です。ただし、適切な管理と有効活用ができないのであれば、固定資産税の支払い義務や管理義務など、相続人にとって大きな負担になってしまうでしょう。そのため、初めから相続放棄で山林を手放した方が、相続人にとってメリットが大きい場合もあります。
また、相続放棄するとすべての財産を手放すことになります。相続放棄で山林のみを手放すことはできないため、注意が必要です。
相続放棄すると相続権は次の順位の相続人に移る
相続放棄すると、相続権は、次の順位の相続人に移るのが原則です。
民法では相続人と相続順位について、次のように規定しています。
| 第1順位:被相続人の子ども(直系卑属) 第2順位:被相続人の両親、もしくは祖父母(直系尊属) 第3順位:被相続人の兄弟・姉妹※被相続人の配偶者は、どの順位においても常に相続人です。 |
上の順位の人が相続放棄をすることで次の順位の人が相続人となります。第1順位の人が全員相続放棄した場合は、第2順位の人が相続人に、第2順位の人が全員相続放棄した場合は、第3順位の人が相続人となり、相続するか相続放棄するかの判断をします。
誰も相続しない場合は最終的に国のものになる
第1順位から第3順位の相続人が全員相続放棄をした場合、遺産を引き継ぐ人がいなくなります。この場合、被相続人が遺した財産は、最終的に国庫に帰属します。
誰も相続しなかった財産は相続財産清算人の選任を経て、被相続人の債権者や遺言によって財産を受け取れる受遺者、内縁の妻などの特別縁故者に分配されます。
そこからさらに相続財産清算人の報酬が支払われたあと、最終的に国に引き継がれます。
相続放棄しても保存義務(管理義務)が残る可能性はある
相続放棄すれば山林の所有者としての地位を引き継ぐことはありませんので、管理義務は課されないのが原則です。
ただし、場合によっては、相続放棄をしたにもかかわらず、山林の保存義務(管理義務)だけが残ることがあります。
相続放棄後に残る可能性のある保存義務とは
相続放棄の時点で、相続財産である山林を「現に占有している」場合には、相続財産であるその山林の保存義務(管理義務)を負います(民法940条1項)。
「現に占有している」とは、当該山林を事実上管理・支配している状態のことを指します。
たとえば、生前、被相続人と一緒に山林を管理していた場合には、現に占有している状態であるといえるでしょう。
また、保存義務(管理義務)とは、その山林の財産的価値を損なわないよう、適切に管理する義務のことです。最低限のメンテナンスや、近隣の住んでいる人に迷惑がかからないような対応をすることが求められます。
保存義務(管理義務)については、山林を相続する他の相続人や、相続財産清算人に引き渡すまで課されるのが原則です。
このように、相続放棄をしても、現に占有している山林については、現状維持しなくてはならない義務だけが残ってしまう可能性があるため、注意しなければなりません。
全員が相続放棄し、保存義務を負ったら相続財産清算人を選任
全員が相続放棄したにもかかわらず、山林の保存義務だけが残ってしまったら、裁判所に相続財産清算人を選任してもらいましょう。
相続財産清算人が選任されれば、山林の保存義務から解放されます。
相続財産清算人とは、相続財産の管理・処分・分配を行う人のことです。残った相続財産から、被相続人の債権者にできる限りの返済をするなどの清算対応を行ってくれます。
最終的に財産を国庫へ帰属させるまでの必要な職務を担っており、山林の管理・処分もすべて相続財産清算人の担当です。
相続人や被相続人の債権者、その他利害関係を有する人は、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に、相続財産清算人の選任を申し立てることができます。
一方、申立てに必要な費用として、相続財産清算人に支払う費用などの予納金が必要な場合があるため、注意してください。
相続や遺言の
無料相談受付中!
-
電話での無料相談はこちら
0120-243-032
受付時間 9:00~18:00
(土日祝日の相談は要予約) -
メールでの
無料相談はこちら

山林を相続放棄すると固定資産税などを支払わなくて済む
相続放棄で山林を手放せば、固定資産税などの税金を支払わずに済みます。
相続することで発生する各種税金や管理を委託する際にかかる費用などを節約できるのは、相続人にとって金銭的なメリットが大きいでしょう。
また、山林の管理を怠ると、草木が公道にはみ出してしまったり、伐採されない木を放置したことによる花粉症被害が発生したりする可能性があります。ときには、周辺住民とのトラブルに発展してしまう可能性もありますが、このようなリスクもなくなります。
さらに言えば、相続したものの山林を活用せずにそのままにしておくと、いずれは自分の子ども世代にその山林が引き継がれてしまい、負担をかけてしまうおそれもあります。
山林を相続放棄で手放せば、これらのデメリットをすべて解決できるのです。
山林を相続放棄する際の注意点
山林を相続放棄する場合、「タイミングによっては固定資産税を支払う必要がある」「相続放棄をしても保存義務が残る場合がある」という2つの点に注意する必要があります。
相続放棄後のトラブルを避けるためにも、これから説明する注意点をしっかり頭に入れておくようにしましょう。
1.相続放棄してもタイミングによっては固定資産税を支払う必要がある
山林を相続放棄すれば、固定資産税を支払う必要がなくなるのが原則です。
しかし、相続放棄のタイミングによっては、相続放棄をしているにもかかわらず、固定資産税の支払義務が発生する可能性があります。
そもそも固定資産税の納税義務者は、1月1日時点で固定資産課税台帳に名前がある人です(台帳課税主義)。
相続放棄をしたらその土地の所有者ではなくなるので、固定資産課税台帳に名前が載ることはなく、固定資産税を支払う義務は発生しません。
一方で、相続放棄したにもかかわらず、固定資産課税台帳に名前が載ってしまった場合には、固定資産税の支払義務が発生してしまいます。
たとえば、年内に被相続人が死亡したものの、相続放棄の申述が受理されたのが年をまたいでしまった場合を考えてみましょう。
年内に亡くなっている以上、被相続人の代わりに誰か別の人が納税義務者になる必要があります。
この場合、各自治体は、法定相続人を相続人であると推定して固定資産課税台帳に登録します。
そのため、相続放棄の手続き中であっても、納税義務者になってしまうことがあるのです。
このように1月1日時点で固定資産課税台帳に名前が載っていると、納税義務の免除は認められません。
2.保存義務を負った際に責任を果たさないと訴えられる可能性がある
相続放棄後の保存義務が残ってしまった場合、適切に山林を管理しないと、第三者や他の相続人、相続財産清算人などに訴えられてしまう可能性があります。
例としては、管理を怠ることで山林の財産価値を下げてしまったことで他の相続人に訴えられてしまうケースや、周辺住民とトラブルになってしまったことで第三者に訴えられてしまうケースを挙げることができます。
そのため、保存義務がある場合は、対応を怠らないように気をつけてください。
ただし、管理義務があるからといって山林に手を加えすぎるのもよくありません。単純承認とみなされ、相続放棄できない危険性もあります。
単純承認とは、被相続人の財産を全て無条件で相続することです。山林を勝手に売却する行為はもちろん、山林の管理にあたって手を加える行為も、場合によっては単純承認にあたる可能性があります。
管理者としてどこまでの対応が必要で、どこからが単純承認に当たるかは、専門的な判断が必要です。管理について不安な点がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄以外で山林を処分する方法
相続放棄では、山林だけを相続放棄することはできません。
他に資産がある場合には、相続放棄をすると金銭的に損する可能性があります。
その場合は、相続土地国庫帰属制度を利用したり、山林を売却・譲渡・寄付したりすることで、他の財産を相続しながら山林だけを手放すことができます。
ここからは、相続放棄以外で山林を処分する3つの方法について解説していきます。
1.相続土地国庫帰属制度を利用して山林のみを手放す
「相続土地国庫帰属制度」なら、管理コストを抑えつつ山林だけを手放せます。
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって不動産の所有者となった場合に、その不動産を国に引き渡せる制度です。
山林を処分する相手を探す必要がないため、負担なく山林を手放すことが可能となっています。また、国が引き取り手になるため、余計なトラブルに発展する可能性がないのも、この制度の大きな特徴です。
ただし、同制度を利用するためには一定の条件を満たす必要があります。
たとえば、山林に担保権や使用収益権が設定されている場合や、土壌汚染や境界線が確定していない場合、管理・処分に通常よりも過分な費用・労力がかかる土地の場合は、申請が却下される可能性があります。
また、審査手数料や、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があることも、頭に入れておかなければなりません。
相続土地国庫帰属制度を利用して山林を手放したいのであれば、申請が却下されない土地であるかどうかを、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
2.相続したうえで山林を売却または寄付して手放す
相続した山林を売却したり寄付したりすることも、山林だけを手放す有効な方法の1つです。
山林近くの不動産業者や、森林組合、自治体を通して買い主を探したり、山林売買を専門で行っている不動産買取業者に引き取ってもらったりするのもよいでしょう。
仲介手数料はかかりますが、個人で引き取り手を探すよりも、スムーズに話が進む可能性が高いです。
また、市区町村などの各自治体や公益法人などの団体、山林を探している個人などに、寄付することも可能です。
ただし、山林の状況次第では、なかなか引き取り手が見つからないケースも珍しくありません。
林業向きの山林であるなど、利用価値がある場合でなければ売却・寄付が難しい可能性もあります。
また、すぐに引き取り主が見つかるとは限りませんので、すぐにでも山林を手放したい場合には、向いていない方法といえるでしょう。
3.相続分の譲渡や放棄によって山林を手放す
相続分の譲渡や放棄をして、ほかの相続人や第三者に山林を引き継いでもらうのも1つの方法です。
相続人が複数いる場合、相続財産をどのように分配するかについて、遺産分割協議を行う場合があります。
遺産分割協議において、自身の相続分は、ほかの相続人や第三者に譲渡できます。
もし、協議の中で、「山林は他の相続人が相続する」ことの合意ができれば、山林だけを相続せずに済む可能性があります。
相続分の譲渡や放棄は、相続放棄と異なり協議の中での取り決めなので、口約束でも有効に成立します。
しかし、あとから言った言わないのトラブルになるのを防ぐためにも、遺産分割協議書や相続分譲渡証明書を作成して、山林を譲渡・放棄したことの証拠を残しておくようにしましょう。
山林を処分せずに活用するのも選択肢の一つ
山林の状況次第では、処分するのではなく、有効活用する方法を考えるのもおすすめです。
山林の活用方法にはさまざまなものがありますが、たとえば、次のようなものがあります。
- 林業を営んでいる人に貸し出す
- 農園を経営する
- 山林をそのまま活かして、キャンプ場やレクリエーション施設にして経営する
- 建築会社や土木会社に資材置き場として貸し出す
- 太陽光発電に利用する
- 産業廃棄物処理場として活用する
など
アイデア次第でさまざまな活用方法が考えられるので、相続放棄をする前に1度リサーチしてみるのもおすすめです。
ただし、山林が市街化調整区域や保安林に指定されている場合、開発が制限されてしまうことで、自身の思い描いている活用法を実現できない可能性があります。
山林を活用することを検討しているのであれば、あらかじめ調べておきましょう。
まとめ
山林は相続財産の一部なので、相続放棄で手放せます。
固定資産税の支払いや手間のかかる管理義務を負うこともなくなるので、今後、山林を活用する予定がないのであれば、相続放棄するのが望ましいかもしれません。
一方で、相続放棄したにもかかわらず、タイミングによっては固定資産税の納税義務が発生したり、山林の保存義務が残ってしまったりするケースもありますし、他に資産があると、それも相続できなくなってしまいます。その際は別の方法で山林を処分することを考えた方が良いかもしれません。
判断にお困りでしたら、一度、みつ葉グループの司法書士までご相談ください。
山林の取り扱いだけでなく、どのような判断が相談者の方にとってメリットが大きいのかを考え、アドバイスをいたします。
ご相談は無料です。山林の相続・相続放棄をみつ葉グループがサポートいたします。
カテゴリ