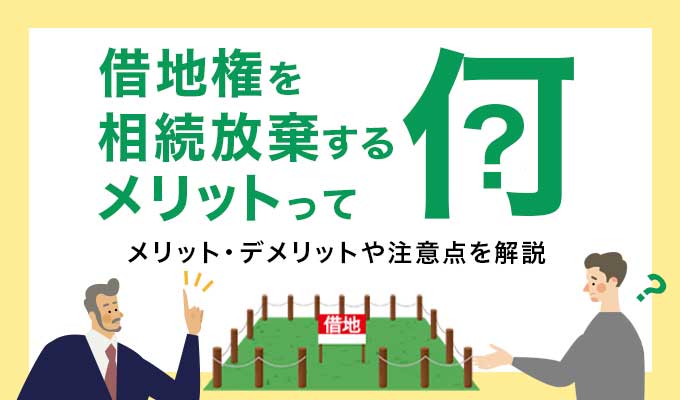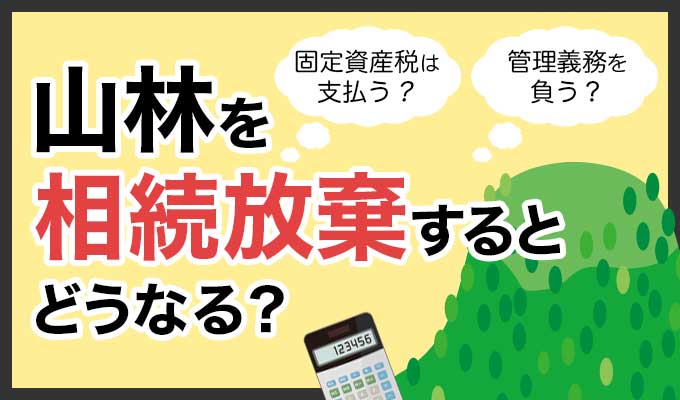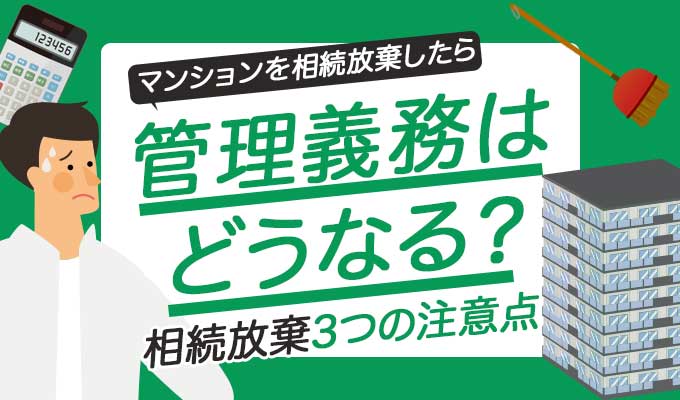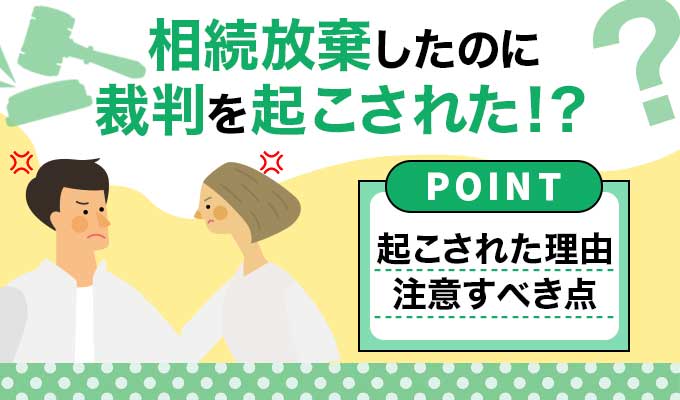相続放棄
相続放棄は3ヵ月経過したら上申書が必要!書き方や注意点を解説
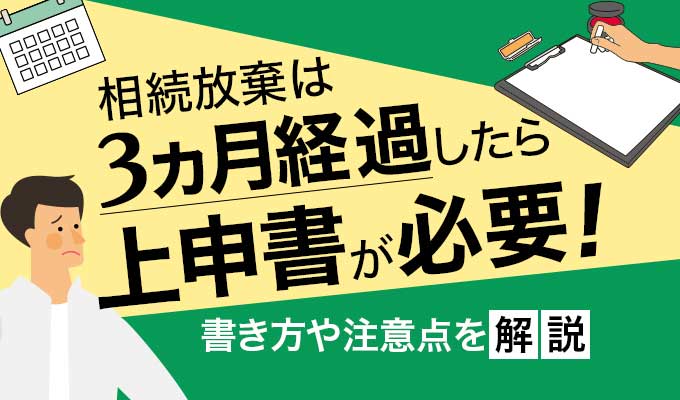
相続財産の調査や必要書類を集めるのに時間がかかってしまった場合、相続放棄の期限を過ぎてしまうケースは珍しくありません。
基本的に、申述期限を過ぎると相続放棄はできなくなります。
しかし、期限内に相続放棄をおこなうのが困難な事情があれば、被相続人の死亡日から3ヵ月を過ぎていても相続放棄が認められる場合があり、その際は「上申書」と呼ばれる書面の提出が必要です。
この記事では、申述期限を過ぎた相続放棄が認められるやすいケースを紹介したうえで、上申書の書き方や提出方法、作成する際の注意点などについてわかりやすく解説していきます。
上申書の書式テンプレートも紹介していますので、ぜひご活用ください。
目次
熟慮期間の3ヵ月経過後の相続放棄は上申書を提出しよう
相続放棄の申述期限は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内です(民法915条1項)。
この期限のことを法律上「熟慮期間」と呼びますが、この熟慮期間は、裁判所に申し立てることで、1〜3ヵ月程度は伸ばしてもらえる可能性があります。
熟慮期間を過ぎてしまった場合の相続放棄では、通常の相続放棄で必要な書類とあわせて、「上申書」を裁判所に提出します。
上申書とは、裁判所に提出する意見書のことであり、特別な事情があって期限に間に合わなかったことを主張するためのものです。
【参考】民法|e-Gov法令検索
上申書の提出により熟慮期間延長が認められやすいケース
3ヵ月より後の相続放棄は、法律で規定している期限を過ぎてしまっている以上、すべてのケースで延長が認められるわけではありません。
しかし、次の3つのケースに該当する場合には、熟慮期間経過後でも相続放棄が認められやすいでしょう。
| 1.相続財産がまったくないと判断しても仕方のない事情があった 2.相続財産調査に時間のかかる事情があった 3.熟慮期間内に借金の存在を認識できない事情があった |
以下で、それぞれのケースについて解説していきます。
1.相続財産がまったくないと判断しても仕方のない事情があった
相続財産がないと思い込んでいた、もしくは相続財産は一切ないと信じ込んでいた場合には、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したときからが熟慮期間となる可能性があります。
この際にポイントとなるのが「相続財産が全くないと判断しても仕方のない事情」があることで、これは次のようなケースであれば、3ヵ月経過した後の相続放棄が認められる可能性があります。
- 被相続人が生活保護を受けており、日頃から相続する財産は存在しないと言っていた
- 生前、被相続人と交流が少なく、財産に関する情報が乏しかった
- 先順位の相続人が相続放棄したことで相続権が回ってきたが、とくに連絡がなかったため、自分に相続権があることを知らなかった
なお、以下のようなケースで、実際の裁判でも熟慮期間を過ぎた相続放棄が認められています。
| 1. 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていたことにより相続放棄をしなかった 2. 被相続人の生活歴や相続人との交際状態などからみて、熟慮期間内に相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情があること 3. 1につき相当な理由があること |
2.相続財産調査に時間のかかる事情があった
相続財産の調査に時間がかかって3ヵ月を経過してしまった場合、その事情を上申書で説明することにより、熟慮期間経過後の相続放棄を認めてもらえる可能性があります。
「ただ遅くなった」では認められる可能性は低く、以下のような、3ヵ月が経過しても仕方ないと思われるような正当な理由が必要です。
- 不動産などの相続財産が全国各地にあり、3ヵ月では調査しきれなかった
- 相続人と被相続人の住所地が離れており、調査に時間がかかった
- 被相続人とずっと疎遠で、住所等がわからず、自宅調査や金融機関などへの照会対応が難しかった
- 不動産や株、有価証券、暗号資産など、相続財産の構成が複雑だった
- 被相続人が事業を経営しており、財産と負債の整理に時間がかかった
- 相続人が海外出張でほとんど日本におらず、財産調査の時間が足りなかった
3.熟慮期間内に借金の存在を認識できない事情があった
相続財産調査をおこなったものの、熟慮期間内に借金の存在を認識できなかった場合も、上申書の内容次第では、熟慮期間が過ぎていても相続放棄を認めてもらえる可能性があります。
相続財産調査で、被相続人の財産すべてが確実に明らかになるわけではありません。
相続財産調査で全財産が明らかにならないケースでは、財産調査を入念におこなわないと相続放棄に踏み切れないことから、熟慮期間満了後の相続放棄が認められる可能性があるのです。
熟慮期間内に借金の存在を認識できないケースとしては、次のようなものが挙げられます。
- 通帳や契約書、郵便物などを確認するだけでは、被相続人の借入状況の全貌を把握できなかった
- 借入状況がわかる書類が破棄されていた
- 専門家に財産調査を依頼したにも関わらず、借金の存在が判明しなかった
相続や遺言の
無料相談受付中!
-
電話での無料相談はこちら
0120-243-032
受付時間 9:00~18:00
(土日祝日の相談は要予約) -
メールでの
無料相談はこちら

上申書の書き方
熟慮期間を過ぎた相続放棄を認めてもらうためには、「なぜ熟慮期間内に相続放棄ができなかったのか」を裁判所に対して主張する必要があります。
そのために上申書に書く内容、書く際のポイントは、次の通りです。
| ● 自分の名前と住所 ● 被相続人の名前 ● 被相続人の死亡日 ● 熟慮期間内に相続放棄ができなかった理由 ● 具体的な事情から「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヵ月経過しているとは言えないこと など |
上申書に決まった書式はなく、文量の目安はA4サイズ1枚程度で記載すれば問題ありません。
自身の状況をとにかく詳細に記載し、裁判例などを引用しながら、熟慮期間経過後に相続放棄を認めてもらうことの正当性を主張することが重要です。
なお、上申書の内容が不十分で相続放棄が認められなかったとしても、改めて上申書を出し直して再審査をしてもらうことはできません。
そのため、上申書の作成は専門家である司法書士のサポートを受けることをおすすめします。
文例|今すぐ使える書式テンプレート
ここで、熟慮期間経過後の相続放棄で使える上申書の作成例をご紹介します。
事案
| 両親が離婚した後、10年以上連絡をとっていなかった父親が死亡した。相続人は、X社から「相続人として借金を支払ってほしい」と連絡がきたことで初めて、父親に借金があったことを知った。 父の死亡からすでに数年経過しており、家族から父の死亡については聞いていたため、相続放棄はできないものと諦めていた。 しかし、司法書士にそのことを相談したところ、もしかしたら「相続できる財産がまったくないと信じるにつき相当な理由がある場合」に該当する可能性があると言われた。 そのため、上申書を添えて相続放棄の申述をおこなった。 |
ポイント
| ・父とは、相続人が幼い頃に両親が離婚して以来連絡をとっていなかった ・父の死亡当時、申述人はまだ高校生であり、財産状況を把握できる状態ではなかった ・母親や長男から、借金を含む相続財産について聞かされたことはなく、被相続人には財産は一切ないものと信じ込んでいた ・たとえ相続財産があったとしても、被相続人と同居している長男が、すべてて相続するものだと考えていた ・X社から通知があったことで、初めて父に借金があったことを知った |
結論
| 被相続人の生活歴、財産の管理状況などを総合的に考えると、熟慮期間内に相続財産の調査を期待することは著しく困難であり、相続できる財産がまったくないと信じる相当な理由があるといえる。 したがって、熟慮期間は「X社から通知が来た日」の翌日から計算すべきで、現時点ではまだ熟慮期間の3ヵ月が経過したとはいえない。 |
【作成例】
|
上 申 書 令和●年●月●日 ●家庭裁判所 ●支部 御中 申述人 山田 太郎 ㊞ 被相続人●(以下、「被相続人」という。)に係る相続について、申述人●(以下、「申述人」という。)が、被相続人の死亡後3ヵ月を経過した現時点において、相続放棄の申述をするに至った経緯などについて上申いたします。 1.経緯 被相続人は令和●年●月●日に死亡したが、被相続人は、申述人が●歳のときに離婚しており、死亡当時、被相続人と申述人は別居していた。 2.熟慮期間の起算点は「X社から通知が来た日」であり、未だ熟慮期間は満了していない点について 申述人は、令和●年●月●日頃、X社からの連絡により、被相続人が、死亡当時、債務を負担していた事実を知るに至ったものである。 よって、熟慮期間は、申述人が、相続財産の全部または一部である上記債務の存在を認識した日の翌日である、令和●年●月●日から起算されるべきものであり、未だ熟慮期間が満了しているとは言えない。 以 上 添付書類 X社からの令和●年●月●日付ご連絡の写し 1通 |
相続放棄の上申書の提出方法
熟慮期間経過後の相続放棄を認めてもらうためには、相続放棄で必要な書類と上申書を家庭裁判所に提出します。
ここでは、相続放棄の際に必要な書類や、書類の提出先について解説していきます。
上申書を含む相続放棄に必要な書類を作成・用意する
熟慮期間を過ぎた相続放棄では、相続放棄申述書および上申書が必要です。
相続放棄申述書は、裁判所のホームページに雛形と記載例が掲載されているので、書式をダウンロードして、必要事項を埋めていく形で書面を作成します。
また、相続放棄の申述で必要になる主な書類は、次のとおりです。
| ・相続放棄申述書 ・上申書 ・亡くなった方の住民票除票もしくは戸籍附票 ・亡くなった方の死亡が記載された戸籍謄本(除籍、改正原戸籍) ・申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本 ・800円分の収入印紙(申述人1人分) ・連絡用の郵便切手(裁判所によって枚数や金額が異なる) |
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出する
相続放棄は家庭裁判所に上記書類を提出しておこないますが、提出先は、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。
「被相続人の最後の住所地」は、住民票や戸籍の附票などで確認でき、申請書類の提出方法は、次の2種類のうちいずれかの方法を選択しておこないます。
- 家庭裁判所の窓口に直接出向いて提出する
- 郵送で提出する
上申書の内容が不十分だと相続放棄できない可能性があるため注意
上申書の内容に不備があったり、熟慮期間を過ぎてしまったことについて説得的に説明できなかったりした場合には、相続放棄が認められない可能性があります。
特別な事情があって、期限内に手続きができなかったことを説得的に伝えるためには、法律の解釈や過去の裁判例などを交えて説明するなど、書き方を工夫する必要があります。
この点、上申書の内容が不十分だったからといって、手続きの途中で上申書を提出し直すことはできません。
そのため、上申書の作成は慎重におこなう必要があるでしょう。
上申書の作成は専門家に依頼すべき
熟慮期間を過ぎた相続放棄における上申書の作成は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
前述したように、上申書は、熟慮期間が過ぎたにもかかわらず相続放棄を認めてもらえるよう、裁判所を説得するための書面です。
「借金を支払いたくないから」などの感情的な主張ではなく、相続に関する法律や判例を基に、熟慮期間である3ヵ月はまだ経過していないことを主張する必要があります。
書き方を工夫しなければ、相続放棄が認められない可能性があり、被相続人の借金を背負うおそれがあります。
この点、相続手続きに精通している専門家であれば、過去に相続放棄が認められたケースを参考にして、内容十分な上申書を作成してもらえます。
また、専門家に相談することで、相続や借金問題に関する総合的なアドバイスを受けられます。
場合によっては、相続放棄以外の有効な解決策を提示してもらえる可能性もあるので、早いうちに専門家に相談しておくことは、非常にメリットが大きいでしょう。
相続放棄が認められなかった際の即時抗告のサポートも依頼できる
専門家に依頼すれば、上申書を添えても相続放棄が認められなかった場合に、即時抗告などのサポートもしてもらえます。
即時抗告とは、家庭裁判所の決定に不服があるときに、再審査を要求できる制度です(家事事件手続法201条9項3号)。
期限は「審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内」で、再審査をおこなうのは高等裁判所です。
申立ては、以下の書面を、相続放棄を申し立てた家庭裁判所に対して提出します。
- 即時抗告の抗告状
- 即時抗告の理由を証する証拠書類
- 収入印紙
- 連絡用郵便切手
ただし、1度相続放棄の審査をおこなっている以上、即時抗告で相続放棄を認めてもらうのは簡単ではありません。
再審査で相続放棄を認めてもらうためには、相続放棄が認められなかった理由や上申書の内容を細かく分析し、相続放棄が認められなかった理由について、再度主張する必要があります。
即時抗告には専門的な知識が必要になるため、相続人個人がおこなうのではなく、専門家に相談・依頼するのが望ましいでしょう。
まとめ
被相続人の死亡から3ヵ月を過ぎている場合でも、上申書を裁判所に提出することで、相続放棄を認めてもらえる可能性があります。
ただし、必ずしもすべてのケースで相続放棄を認めてもらえるわけではなく、熟慮期間内に相続放棄の手続きを取ることが困難であったことを、法的な観点から主張する必要があります。
上申書は自分で作成もできますが、相続に関する法律や解釈、過去の裁判例などを用いて内容を記載する必要があるため、できれば専門家に作成を依頼するのが望ましいでしょう。
3ヵ月が経過した後の相続放棄が認めてもらえるのは例外的なケースで、簡単な手続きではありませんが、認められる可能性は残されています。
相続放棄に詳しい司法書士に相談し、上申書の作成などを進めていきましょう。
相続放棄をサポートしてくれる専門家をお探しでしたら、司法書士法人みつ葉グループまで、お気軽にご連絡ください。
カテゴリ